モラハラ後遺症に苦しむあなたへ
「モラハラ関係から抜け出したのに、苦しみが続いている…」
「自分に自信が持てない…何をしてもダメな気がする。」
「他の人もモラハラしてくるんじゃないかと、ずっとビクビクしている。」
モラハラから離れたのに、心と体の症状が消えな。
それは、モラハラ後遺症かも知れません。
モラハラ後遺症とは、モラハラを受けた後に残る 心理的・身体的な症状のこと。 PTSD(心的外傷後ストレス障害)、 うつ病、不安障害など、 深刻な影響を及ぼすことがあります。
この記事では、モラハラ・恋愛依存・愛着問題専門カウンセラーが、 モラハラ後遺症の症状、原因、そして克服法を実際のクライアントの回復事例とともに詳しく解説します。
【この記事でわかること】
✔ モラハラ後遺症の15の症状
✔ 症状チェックリスト
✔ なぜ後遺症が残るのか
✔ PTSD、うつ病、不安障害との関係
✔ 克服する5つのステップ
✔ 実際に回復した方の事例
✔ カウンセリングでできること
モラハラは 「離れたら終わり」ではありません。
むしろ、モラハラから抜け出した後こそ、 「本当の自分を取り戻す」ための大切な時間です。
モラハラとは?
モラハラとは、「モラル・ハラスメント」の略で、威圧的な言動や行動で相手を精神的に追い詰める行為をいいます。
暴力とは異なり、直接的な身体的危害を伴わないため、周囲から気づかれにくい特徴があります。
特に、恋人や夫婦間で行われることの多いモラハラは、人格を否定したり、無視や威圧など、許されるものではありませんが、”一般的な喧嘩”との区別がはっきりしないため、周りからはわかりにくく、当事者になっても、「どこもこのくらいはある」と感じて我慢を選びがちになってしまいます。
モラハラについてより詳しい内容は、こちらの記事をご覧ください▼
▶モラハラとは?【モラハラの特徴7選】その特徴、影響、そして対処法を徹底解説
モラハラ後遺症とは?
モラハラから抜け出したはずなのに、慢性的な心の不調が続いたり、不安感や人に対して恐怖心を持ってしまうことがあります。
これは、「モラハラ後遺症」と呼ばれ、モラハラ環境の中でうえつけられた心理的トラウマや思考・感情のパターンが、モラハラ環境を抜け出した後もあなたの心と体い残っているからです。
モラハラ後遺症とは、 モラハラ(精神的虐待)を受けた後に残る 心理的・身体的な症状の総称です。正式な医学用語ではありませんが、 多くの被害者が経験する現実の症状です。
モラハラは、物理的な暴力と違い「言葉・態度・支配」で心をじわじわ蝕んでいきます。
そしてその影響は、別れた後や距離をとった後も長く残り続けてしまうことがあります。
特に、長期的にモラハラを受けていた方は、自分でも気が付かないうちに「自分を責める思考」「無意識の恐怖」「過剰な警戒心」などが染み付いています。
つまり、「別れた=解決」ではなく、本当の回復には別れたあとのケアが必要です。
なぜ「後遺症」が残るのか
モラハラは、脳に深刻なダメージを与えます。
脳科学的な説明
1.扁桃体の過活動
恐怖を感じる脳の部位が過敏になる → 些細なことでも怖くなる
2.海馬の萎縮
記憶を司る部位が小さくなる → 記憶があいまい、フラッシュバック
3.前頭前野の機能低下
理性を司る部位が弱まる → 感情のコントロールが困難
4.ストレスホルモンの慢性的分泌
コルチゾールが常に高い状態 → 疲労、不眠、免疫力低下 → これらの脳の変化が「後遺症」を引き起こす
モラハラ後遺症とPTSDの関係
モラハラ後遺症の中で最も深刻なのがPTSD(心的外傷後ストレス障害)です。
PTSDとは: 強い恐怖体験の後に起こる心の病気
モラハラは、PTSDを引き起こす 十分な「トラウマ」になり得ます。
【無料診断】モラハラ後遺症チェックリスト
以下の症状に当てはまるか、チェックしてください。
Part 1:フラッシュバック・侵入的思考(5項目)
Part 2:過覚醒・緊張(5項目)
Part 3:回避・麻痺(5項目)
Part 4:自己評価の低下(5項目)
Part 5:身体症状(5項目)
診断結果
0-5個:後遺症は軽度
モラハラの影響はあるものの、日常生活に大きな支障はない状態。セルフケアで改善できる可能性があります。
6-15個:中程度の後遺症
モラハラの影響が残っている状態。専門家への相談を検討してください。早めの対処で回復が早まります。
16-25個:重度の後遺症(PTSD の可能性)
深刻な後遺症が残っています。一人で抱え込まず、専門家 (カウンセラー、心療内科医)に相談を検討してください。
モラハラ後遺症の15の症状
心理的症状(10個)
1.フラッシュバック
症状:モラハラを受けた時のことが、突然、鮮明に思い出される。まるで「今、その場にいる」かのように 感じることもあります。
具体例:テレビで怒鳴るシーンを見ただけで、当時の恐怖が蘇る。似た声を聞いただけで体が硬直する。ふとした瞬間に、相手の顔が浮かぶ。など
なぜ起こるのか:脳の海馬と扁桃体の機能不全により、過去の記憶が「現在の危険」として誤認識されてしまうため。
2.過覚醒(常に緊張状態)
症状:常に緊張していて、リラックスできない。些細な音や動きに過剰に反応する。
具体例:玄関の音がするだけで、心臓がドキドキする。誰かが近づくと、反射的に身構える。常に「何か悪いことが起こるのでは」と警戒。など
なぜ起こるのか:モラハラ環境では常に警戒が必要だった。その状態が脳に刻まれ、安全な環境でも警戒し続けてしまう。
3. 回避行動
症状:モラハラを思い出させるものを避ける。
具体例:外出が怖い、人と会うのが怖い、特定の場所に行けない、恋愛ができない、人を信じられない
なぜ起こるのか:トラウマから自分を守るための防衛反応。
4. 感情の麻痺
症状:何も感じなくなる。喜びも悲しみも感じない。
具体例:楽しいはずのことも楽しくない、涙も出ない、「自分は生きているのか」と感じる
なぜ起こるのか:強すぎる苦痛から心を守るため、感情をシャットダウンしてしまう。
5. 自己肯定感の極度の低下
症状:自分には価値がないと思い込む。
具体例:「私はダメな人間だ」「誰も私を愛さない」「生きている意味がない」
なぜ起こるのか:モラハラ加害者からの人格否定が深く刻み込まれてしまったため。
6. 人間不信
症状:人を信じられなくなる。
具体例:優しくされても「裏があるのでは」と疑う、人の言葉を素直に受け取れない、親しい関係を築けない
7. 罪悪感と自責
症状:「自分が悪かった」と思い続ける。
具体例:「私がもっと〇〇していれば」「私が我慢すればよかった」加害者を責められない
8. 将来への絶望
症状:未来に希望が持てない。
9. 感情のコントロール困難
症状:些細なことで怒ったり、泣いたり。
10. 判断力の低下
症状:決断ができない、自分の考えがわからない。
身体的症状(5個)
11. 不眠・悪夢
12. 慢性的な疲労
13. 頭痛・めまい
14. 消化器系の不調
15. 免疫力の低下
なぜモラハラ後遺症が起こるのか
モラハラ後遺症は、偶然起こるものではありません。脳と心に深刻な影響を与える、科学的な理由があります。ここでは、後遺症が残る4つの主要な原因を詳しく解説します。
1.長期的なストレスによる脳の変化
モラハラ環境では、長期間にわたって強いストレスにさらされ続けます。この慢性的なストレスが、脳の構造そのものを変化させてしまうのです。
具体的な脳の変化
扁桃体の過活動
恐怖や不安を感じる脳の部位(扁桃体)が過敏になり、些細な刺激でも「危険だ」と反応するようになります。これがフラッシュバックや過覚醒の原因です。
海馬の萎縮
記憶を司る海馬が小さくなり、記憶の整理ができなくなります。そのため、過去の出来事が「今起きていること」のように感じられ、フラッシュバックが起こります。
前頭前野の機能低下
理性や判断を司る前頭前野の働きが弱まり、感情のコントロールが困難になります。これにより、些細なことで怒りや悲しみが爆発したり、冷静な判断ができなくなったりします。
ストレスホルモンの慢性的分泌
コルチゾール(ストレスホルモン)が常に高い状態が続き、疲労感、不眠、免疫力低下などの身体症状が現れます。
これらの脳の変化は、モラハラから離れた後も簡単には元に戻りません。だからこそ、「後遺症」として症状が残るのです。
2. トラウマティックボンディングの名残
トラウマティックボンディング(外傷的な絆)とは、暴力と優しさを繰り返されることで形成される、加害者との強い心理的結びつきのことです。モラハラ関係から離れた後も、この「絆」の影響が残り続けます。
なぜ名残が残るのか
「恐怖と安心」のセット
モラハラのサイクル(爆発期→ハネムーン期→緊張期)を繰り返す中で、脳は「恐怖の後には安心が来る」というパターンを学習しました。この学習が深く刻まれているため、離れた後も「相手がいないと不安」「戻りたい」という矛盾した感情が湧いてきます。
加害者への執着
理性では「あの人は悪い人だった」とわかっていても、感情レベルでは「あの人しかいない」「あの人の優しさが忘れられない」と感じてしまいます。これは、あなたが弱いからではなく、トラウマティックボンディングという脳の反応なのです。
自己否定の内在化
「お前はダメだ」「お前には価値がない」という加害者の言葉が、あなた自身の内なる声として残り続けます。加害者がいなくなっても、その声が自分を責め続けるのです。
このトラウマティックボンディングの名残が、「別れたのに忘れられない」「復縁したくなる」という後遺症を引き起こします。
モラハラのサイクルについて詳しくはこちら▼
▶【診断チェックつき】モラハラと共依存の関係|なぜ別れられない?抜け出す5つのステップと事例
https://akko.site/attachment-love/moral-harassment-2/
3. 学習性無力感
学習性無力感とは、「何をしても無駄だ」「自分には何もできない」という深い無力感のことです。モラハラ環境では、何度努力しても状況が改善せず、この無力感を学習してしまいます。
どのように学習されるか
繰り返される失敗体験
モラハラ環境では、どれだけ頑張っても相手の機嫌は良くならず、むしろ怒られます。「相手の機嫌を取ろう」「良い妻・恋人でいよう」と努力しても、結果は同じ。この繰り返しが、「私には何もできない」という無力感を生み出します。
自己効力感の喪失
「自分の行動で状況を変えられる」という感覚(自己効力感)が完全に失われます。そのため、モラハラから離れた後も、「自分で人生を選択できる」という感覚が持てず、決断ができなくなります。
諦めのパターン
脳は「努力しても無駄」というパターンを学習し、新しいことに挑戦する前から諦めてしまうようになります。「どうせうまくいかない」「私には無理」という思考が自動的に浮かんでくるのは、学習性無力感が原因です。
この学習性無力感が、「自分で決められない」「行動できない」「将来に希望が持てない」という後遺症として残ります。
4. 自己同一性の崩壊
自己同一性(アイデンティティ)とは、「自分は何者か」「自分はどんな人間か」という感覚のことです。モラハラは、この自己同一性を根底から破壊します。
なぜ崩壊するのか
人格否定の繰り返し
「お前は何もできない」「バカ」「価値がない」という言葉を何度も浴びせられることで、「本当の自分」がわからなくなります。「私は本当にダメな人間なのか?」「私には価値がないのか?」と、自分自身を疑い始めます。
相手の価値観の内在化
長期間、相手の価値観に支配されることで、自分の価値観が失われます。「私は何が好きだったのか」「私は何がしたかったのか」さえわからなくなり、すべて相手の基準で判断するようになります。
自分の感情の否定
モラハラ環境では、自分の感情を表現することが許されません。怒り、悲しみ、喜びなど、すべての感情を抑圧し続けた結果、「自分が何を感じているのか」すらわからなくなります。感情がわからなければ、「自分が何者か」もわかりません。
役割への固定化
「世話をする人」「我慢する人」「犠牲になる人」という役割に固定され、それが自分のアイデンティティになってしまいます。その役割から離れると、「私は誰?」という空虚感に襲われます。
この自己同一性の崩壊が、「自分がわからない」「空っぽの感覚」「生きている実感がない」という後遺症として残るのです。
これら4つの原因が複合的に作用する
モラハラ後遺症は、これら4つの原因が複雑に絡み合って起こります。
- 脳の変化により、感情や記憶の処理が困難になる
- トラウマティックボンディングにより、加害者への執着が残る
- 学習性無力感により、行動する力が失われる
- 自己同一性の崩壊により、自分を見失う
→ これらが同時に起こるため、「モラハラから離れたのに苦しい」という状態が続くのです。
しかし、安心してください。
これらはすべて、適切なサポートと時間があれば回復できる可能性があります。脳は可塑性(変化する能力)を持っているため、新しいパターンを学習し直すことができます。
実際に、クライアントさんの中には、こういった症状を抱えながら、自分を取り戻していった方が沢山いらっしゃいます。
合わせて読みたい▼
▶恋愛依存とは?|原因・特徴・克服法を徹底解説
よくある相談内容と共通する悩み
実際に、モラハラ経験のある方からは、以下のようなご相談がとても多く寄せられています。

職場や友人関係でも、自分が責められるのではないかといつも体が緊張してしまう癖がありました。
周りの人はそんなことしてきたことないのに、どうしてもモラハラ環境の中で責められ続けた記憶が体から向けなくて、何かを伝える時にも勇気が必要だったり、身構えてしまっていました。
モラハラは抜け出したら終わりだと思っていたけれど、職場や友人関係などに出る影響が大きくて驚きました。

いいなと思う人が出来ても、この人もモラハラするんじゃないかって臆病になってしまい、恋愛することが怖くなってしまったこともあります。
勇気をだして新しい恋愛をしてみましたが、相手の顔色を伺って過敏に反応してしまい、心が落ち着く関係性を作ることが難しくなってしまいました。
次の恋愛は、絶対に失敗したくなかったので、モラハラ環境の中で失った自信を取り戻して、恋愛で安定的な関係性を作れるように心の土台作りに取り組みました。

仕事をしていても、どうせ私なんかと自分を否定してしまうクセがついて、自信が持てなくなっていました。
せっかくモラハラから別れられたのに、もう私を否定してくる人はいないはずなのに、それでも長い間言われ続けてきた「お前なんか何も出来ない」という言葉が私の心の奥にずっと残っていて、怖くなってしまいました。
少しずつ自分に自信を取り戻しながら、彼が今まで私に言ってきた否定的な言葉は、事実ではないんだと認識していきました。

本当に彼と離れてよかったのか…頭では酷いことする人だし、幸せになれないってわかっていても、時々彼を思い出しては、心がきゅーっとしました。
離れた方がよかったに決まっているのに、戻りたくなってしまう自分にも自己嫌悪でした。
今ではすっかり平気になれたし、別れたよかったと心の底から思えますが、サポートがなかったら、もしかしたら、寂しさに負けて戻っていたかもなと思うと、怖いです。
上記は、これまでご相談をお受けしてきた方のお悩みを個人が特定されない形で、載せさせていただいたものです。
こうした悩みの根本には、モラハラ環境の中で身についてしまった、思考・感情のパターンが抜けていないことがあります。
あなたの心を縛っているその苦しさには、ちゃんと理由があるのです。
モラハラ後遺症を克服する6つのステップ
モラハラ後遺症は、「時間が経てば自然に治るもの」ではありません。
むしろ、何もしないでいると次の人間関係や恋愛で同じパターンを繰り返してしまうこともあります。
ここでは、モラハラ後遺症から抜け出し、「本当の自分」を取り戻すための6つのステップをご紹介します。
ステップ①「事実を分けて捉える練習をする」
✔相手の言っていることが本当にすべてだろうか?
✔「本当に私はダメな人間なのか?」と冷静に考える
モラハラ被害者は、
- 私が悪かったから怒られた
- ダメだって言われたから、私は本当にダメなんだ
と、モラハラ加害者の言葉 = 事実 だと、受け取ってしまっていることがあります。
相手の言っている理不尽を真に受けているとどんどん洗脳が進んでいき、あなたの認知も歪んでいきます。
- モラハラ加害者の発言はその人の意見や場合によっては操作であり、「事実」ではないと知る
- 「相手がそういった」という事実と、あなたがそれを受け入れるかどうかは別でいいんだと知る
分けて考えることで、自分の価値観を取り戻していきましょう。
ステップ②「自己肯定感を少しずつ回復させる」
自己肯定感がボロボロに削られるのがモラハラ環境です。
「自分を責めない」「自分を大切にする」感覚を少しずつ取り戻していきましょう。
具体的には、
- 日記をつける:毎日の出来事と感情を書き、自分の感じたことを受け入れて寄り添ってあげましょう。今日できたことや、感謝を書くのもおすすめです。
- 趣味を持つ:自分の好きなことに没頭している時間というのは、自分自信に喜びを与えてくれて、気持ちも元気になります。
- 自己肯定感を高めるワーク:日常生活の中で、どんな自分でも受け入れてあげて、「頑張っているね」など心の中で声を抱えてあげてください。自分で自分を肯定してあげましょう。
以下の記事では、モラハラと自己否定感について解説してます▼
▶自己否定感を強めるモラハラ環境
ステップ③「他人との境界線を引く練習をする」
モラハラ被害者は、相手の感情や行動に振り回されやすく、他者との境界線を持つことが苦手である人が多いです。
相手の問題を代わりに背負ってしまい、相手が自分でなんとかすべき問題を代わりに解決しようとしてしまいます。
相手にコントロールされ続けた結果、自分の意見や感情を抑える習慣がつき、相手の考えを自分のものとして受け入れてしまうのです。
- 他人の問題に巻き込まれる
- 相手の機嫌で行動を決めてしまう
- ノーと言えず、我慢が当たり前になっている
このような傾向のある人は、他者との境界線を明確にし、相手に依存しない練習をしましょう。
具体的には、
- 私の問題?相手の問題?と区別する
- 頼まれごとに即答せず、一度考えてみる
- 自分一人の時間を持つ
- 自分の感情を感じていく
ステップ④「自分軸を取り戻す」
長くモラハラ環境にいた人は、「何をしたいか」よりも「どうすれば怒られないか」で動くクセがついてしまいます。
✔日々の選択を、相手の求めていることではなく、自分の意志で決めてみる
✔「本当は私はどうしたいのか?」を意識する
出来る範囲からで大丈夫です。
いきなり、モラハラ加害者に自己主張するというのは、これまでの関係性を考えてもハードルが高いと思います。自己主張は自分の気持ちを受けいれてくれそうな、友人などから練習してみてください。
ステップ⑤「安心できる人間関係を広げる」
✔モラハラ加害者以外の、他の人の評価を聞くことで自分の価値を再確認する
✔「信頼できる人」と繋がり、心の安全基地を作る
モラハラ加害者とだけの人間関係しかないと、相手の言葉がすべてになってしまいます。
モラハラ環境による洗脳も強まっていきます。
出来るだけ広い人間関係を持ちましょう。
ステップ⑥「思考のクセを少しずつ手放す」
モラハラ後遺症では、ネガティブな「思考グセ」が心に根を張っています。
- どうせ私はダメ
- また同じ目に遭うんじゃないか
- 自分の意見を言ったら嫌われる
思考グセを手放すために取り組んで欲しいこと
- 思ったことを、いったん紙に書き出して「本当にそう?」と問いかけてみる
- 過去の体験と、今、目の前の出来事を切り離して考える
- 「もし友達が同じことを言っていたら、どう返すか?」を考えてみる
まとめ:後遺症を克服し、本当の自分を取り戻すために
モラハラは、「別れたら終わり」ではありません。
むしろ、別れた後のケアこそが、スタートラインです。
そう感じてしまうのは、あなたの意思が弱いからではなく、長期間にわたって刷り込まれてしまった“思考のクセ”と、深い愛着やトラウマの影響がまだ心の中に残っているからです。
モラハラ後遺症は、全てが時間がたてば自然とよくなるものでもありません。
むしろ、何もしないでいると、染み付いたネガティブな思い込みが強化されていき、ますます抜け出せなくなってしまうこともあります。
トラウマになっている場合、自分一人で解決しようとすると、逆に心の負担が増えてしまうことがあります。
また、取り組むべき方向性を間違えてしまったり、自己肯定感がどうしても下がっている状態なので、うまくいかないことでさらに自分を責めてしまうということもおこりやすいです。
本やネットで調べれば、知識は手に入りますが、実は知識があることと、症状が改善できることは、全く違うスキルです。
そんな時は、一度専門家の視点から整理してみることで、驚くほどスムーズに前に進めることがあります。
一人で頑張りすぎてしまうあなただからこそ、一度頼りに来てください。
関連記事
モラハラから抜け出した後も、 また同じような相手を選んでしまう方は、こちらの記事をお読みください▼



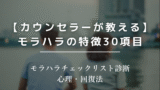


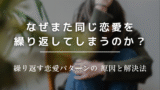
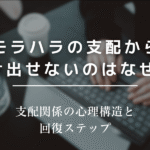
コメント