「どうせ私なんか…」
「うまくいっても、“たまたま”だと思ってしまう」
「誰かに認められないと、不安になる」
――それ、もしかすると“自己肯定感の低さ”かもしれません。
恋愛がうまくいかない、人間関係で疲れやすい、自分に自信が持てない。
どんな悩みも突きつめていくと、たどり着くのは「自己肯定感」という土台です。
でも、そもそも「自己肯定感ってなに?」「高めればいいの?」と、なんとなく聞いたことはあっても、その正体をきちんと理解している人は多くありません。
このガイドでは、
- 自己肯定感とは何か?
- なぜ自己肯定感が低くなるのか?
- どうすれば健全な自己肯定感を育てられるのか?
――について、解説します。
恋愛も、仕事も、人間関係も。
「自分をどう見ているか」が、人生のすべてを決めていきます。
だからこそ、“本当の意味での自己肯定感”を理解し、自己肯定感をとりもどしていくことが必要です。
自己肯定感とは?――自己肯定感の誤解
「自己肯定感が低いんです」
「もっと前向きに考えられるようになりたんですけど……」
そう話す人の多くは、「ポジティブでいる力」や「自信満々な状態」だと誤解しています。
自己肯定感とは、何かができる・できないという「結果」や「能力」の話ではありません。
また、「自分大好き!」と自信満々にふるまうことでもありません。
自己肯定感とは、“自分は大切な存在であるという感覚”
自己肯定”感”ですから、自分を肯定する”感覚”のことです。
結果や能力、周りからの評価など外側のものに一切左右されず、「自分は、何ができても、できなくても、大切な存在である」と感じられる感覚のことです。
例えば、
- お気に入りの服を着たから、自己肯定感が上がった
- 〇〇の試験に合格したから、自己肯定感が上がった
などと感じる人も多いかも知れませんが、こうした感覚は、正確には「気分が良い」「一時的に高揚している」だけ。自己肯定感とは、外側の条件に左右されない、“無条件の自己価値”に基づく感覚です。
自己肯定感が「低い」とどうなる?
- 頑張っても認められないと、すぐ自己否定してしまう
- 褒められても「たまたまだ」と、評価を受け取れない
- 他人の期待に応えようと無理をしがち
このような状態は、「自分の存在価値は、◯◯できているときだけ」という条件つきの自己価値感(偽物の自己肯定感)が根っこにあるためです。
いくら努力しても、いくら結果を出しても、「これでいい」と心の底からは思えない状態です。
自己肯定感が低いのは「持って生まれた性格」ではない
「私は自己肯定感が低いタイプだから…」とあきらめる必要はありません。
実は、みんな生まれた瞬間は自己肯定感がある状態で生まれてきます。
赤ちゃんから3歳くらいまでの子供を想像してみてください。
他人と比べて落ち込んだり、自分が何かが出来ないから自己否定したり、しないですよね。
ただ存在しているだけで、自分の価値を疑っていない。
これが、私たちの“本来の姿”なのです。
私たちは、みんな自己肯定感がある状態で生まれているんです。
だから、“低いまま一生変わらない”ということはありません。
自己肯定感は、どこかで失ったもの。
つまり、「取り戻す」ことができる感覚です。
この先の章では、なぜ失われたのか、どうすれば再び根づかせていけるのか、具体的に解説していきます。
自己肯定感が低くなる原因とは?
自己肯定感が「生まれつき低い」わけではないのなら、なぜ私たちは、こんなにも“自信が持てない自分”になってしまうのでしょうか?
それは、これまでの人生のなかで――とくに幼少期の体験を通して、少しずつ形成された“心の前提”です。
条件付きの愛がつくる「偽りの自己価値感」
本来、自己肯定感とは「何ができても、できなくても、自分には価値がある」と感じられる感覚です。
でももし、子どもの頃に
- 「いい子にしていなさい」
- 「ちゃんとやらないとダメ」
- 「お兄ちゃん(お姉ちゃん)なんだから我慢して」
そんな“条件付きの愛”を繰り返し受け取ってきたとしたら――
心の奥には、
「私は〇〇しないと価値がない」
「頑張らないと、認められない」
という前提が深く刷り込まれてしまうことがあります。
「親の態度」は「心の土台」になる
親の何気ない一言や態度は、子どもの心にとって「世界そのもの」です。
たとえば、
- 成績がよい時だけ褒められた
- 我慢した時だけ優しくされた
- 甘えた時に拒絶された
こうした体験は、大人のあなたが思っている以上に心の土台に強い影響を与え、大人になってからも影響し続けています。
そしてその価値観は、「やっぱり私は〇〇しないとダメなんだ」と思い込ませるような出来事を、無意識のうちに引き寄せ、何度も繰り返してしまうのです。
否定的なセルフトークが、さらに自己肯定感を削る
大人になったあなたは、日常の中で、自分に対してどんな言葉をかけていますか?
たとえば…
- 「こんな自分じゃダメだ」
- 「また失敗した」
- 「もっと頑張らないと」
こうした否定的なセルフトーク(自己内対話)は、
自己肯定感をじわじわと削っていきます。
自己肯定感が低いからこそ、こうした否定的なセルフトークが習慣になりやすく、
そのセルフトークがさらに自己肯定感を下げていく――
この“負のループ”が、あなたの心を知らず知らずのうちに消耗させていきます。
自己肯定感が低いとどうなる?
自己肯定感が低いと、私たちの対人関係・恋愛・仕事など、人生のあらゆる場面に影響を及ぼします。
「なんとなく生きづらい」と感じている人の多くは、自分でも気づかないうちに、この“自己肯定感の低さ”を土台に日々を過ごしているのです。
この章では、自己肯定感の低さがどのように日常に表れるのか、3つの視点から解説します。
1. 対人関係|“いい人”でいなきゃと思ってしまう
- つい相手の顔色をうかがってしまう
- 断れない、頼まれるとNOと言えない
- 嫌われるのが怖くて、本音が言えない
…そんなふうに、「相手を優先しすぎる」クセがあるとしたら、それは自己肯定感の低さと深く関係しています。
自己肯定感が低い人は、「自分の感情やニーズを後回しにしないと安心できない状態」が心の根本にあります。
この状態で相手を優先するのは、「優しさ」や「思いやり」ではなく、一種の自己防衛(自分を守るための)行動です。
2. 恋愛|“愛されていないかも”という不安がつきまとう
恋愛は、「愛着」の問題が中核にあるものですが、自己肯定感も深く関係しています。
- LINEの返信が遅いと、不安で仕方ない
- 「嫌われたかも」「重いと思われたかも」と何度も考える
- 自分ばかりが頑張っていると感じる
こうした不安や過剰な自己犠牲は、「自分には価値がないから大切にされるわけがない」「愛されるために頑張らなければならない」というような思い込みからきています。
自己肯定感が低いと、「ただそこにいるだけの私」が愛される実感を持ちづらくなり、“尽くすことで価値を得ようとする”恋愛になってしまいやすいです。
愛着についてはこちらも合わせてお読みください▼
恋愛依存と愛着|“どうしても離れられない私”から抜け出す完全ガイド
3. 仕事・自己実現|結果を出しても、自信が持てない
「まだまだ」「私なんて」と思ってしまう
- うまくいっても「たまたま」と感じる
- 失敗やミスが怖くて、行動できない
どれだけ成果を出しても「自分の価値」として受け取れないのは、内側の自己評価が育っていないからです。
そのため、常に“誰かに認められたい”“もっと頑張らなきゃ”と追い立てられるような感覚になり、自己実現どころか、日常をこなすだけで消耗してしまいます。
「高める」のではなく、「整える」
ここで大切なのは、「自己肯定感を高めよう」と無理をすることではありません。
本来、自己肯定感は「つくるもの」ではなく、「取り戻すもの」。
すでに持っていた“ありのままの自分にOKを出せる感覚”を、もう一度自分の内側に取り戻していくことが、自己肯定感の“再設計”です。
偽りの自信も、自己肯定感の低さの裏返し
自己肯定感が低いと、自信がないどころか、逆に“過剰に自信満々”にふるまう人もいます。
実はこれ、無意識の自己否定を隠すための「防衛反応」です。
「なにがなんでもすごいと思われなきゃ」「負けたくない」という強い欲求の裏には、「本当の自分は認めてもらえないかもしれない」という不安が隠れているのです。
自己肯定感を知らずに下げてしまう5つの“無意識のクセ”
自己肯定感が低い人の多くは、“日常の思考”や“行動のクセ”によって、さらに自分の自己肯定感を削ってしまっています。
この章では、自己否定を深めてしまう5つの代表的なクセを解説します。
1. 役に立ってないと、愛されない
「役に立っていないと、自分には価値がない」と感じる人は多くいます。
- 頼られていないと不安になる。
- 何もしていない自分を無価値に感じる。
- 恋愛や仕事で「がんばりすぎる」クセがある
そんな感覚があるとしたら、それは「役に立たなければ」という思い込みが強いかも知れません。
こういう人は、役に立つために、わざわざ「ダメな人」を作り上げる、恋愛でいうと「ダメンズメーカー」になってしまうこともあります。
「役に立つことでしか、自分の存在価値を感じられない」というクセは、“他人軸”の典型です。
自分を愛してくれる人より、「自分が支えなければ壊れそうな人」をわざわざ選んで、苦しい恋愛を繰り返してしまいます。
合わせて読みたい
ダメンズメーカーになりやすい女性の特徴とその原因とは?
2. 他人の期待が“自分の基準”になっている
自分の気持ちよりも、相手に”どう思われるか”を優先してしまい、自分がどうしたいかよりも、相手が何を求めているかを自然と汲み取って行動してしまうことが、クセになっていないでしょうか?
自己肯定感が育つには、“自分の価値基準”が必要ですが、それがよくわからないままだと、どこまでも他人に振り回されてしまいます。
3. 安心より「緊張」に慣れている
幼少期に、怒鳴られたり、無視されたり、感情の安定しない環境で育った人は、「安心」より「緊張」に慣れていることがあります。
- 安定した人間関係が落ち着かない
- 優しくされると、なぜか居心地が悪く感じる
- ドキドキ・ハラハラの恋愛しかできない
これは、安心感を感じられる状況に、心が慣れていないだけかも知れません。
4. 完璧じゃないと自分を許せない
- 少しの失敗で「もうダメだ」と思ってしまう
- 「まだまだ…」といつも努力し続けてしまう
- 息を抜くことに罪悪感を感じる
“できている自分”だけを受け入れようとしていませんか?
ミスや失敗をしてしまうそんな自分も含めて全部が自分です。
自己肯定感が低い人は、“ありのままの自分”を受け入れることが難しくなっています。
何かが出来ることで自分の価値を保とうとしてきた人は、ミスや失敗をすることで自分の価値が保てなくなってしまうと思い込んでいます。
5. 自分の感情にフタをしている
- 「本音がわからない」
- 「泣きたいのに泣けない」
- 「人前では平気なふりをしてしまう」
こうした人は、感情にフタをすることで”自分を守ってきた”過去があるかもしれません。
苦しい環境、安心できない環境に長い間いると、その苦しさを感じることが辛いので、自分を守るために、何も感じないようになっていくことがあります。
また子供の時に、感情を表現することで怒られてしまったり、親の感情表現が乏しいと、自分も感情を抑え込むようになってしまいます。
まずは、「自分の中にある前提」に気づくこと
これらは、すべてこれまでの環境に適応して、身に着けた戦略でもあります。過去のあなたを守ってきたものです。
ですが、大人になった今、その戦略が自分を苦しめてしまっているのなら、手放していくことが必要です。
これまでの思い込みを責める必要はありません。
でも、もし今の生き方に「苦しさ」があるなら──
必要のない前提は手放していきましょう。
自己肯定感を育てるおすすめワーク3選
自己肯定感を取り戻すといっても、具体的に何をすればいいかわからない…という人も少なくないと思います。
ここでは、日常の中で出来る、今日からさっそく取り組めるシンプルだけど効果的な自己肯定感の土台作りワークを3つ紹介します。
1.「これがいい!」で選ぶ
シンプルだけど、実はとても効果的なワークです。
特に、モラハラ環境など日常的に自分を我慢させる環境で長く過ごしてきた方は、自分の気持ちがわからなくなっています。
- 相手が求めるものを選ぶ
- これ”で”いいや…
こういう選択を繰り返すことで、自分の本当の気持ち、何をしたいか、何がいいのか、どんどんわからなくなっていくし、自己肯定感も削られていきます。
周りに合わせるのではなく、「私はこれがいい!」という自分の気持ちで選ぶ練習をしていきましょう。
徐々に自分の気持ちが取り戻されていくのを感じるはずです。
合わせて読みたい
モラハラとは?【モラハラの特徴7選】その特徴、影響、そして対処法を徹底解説
2.NOを言う練習ワーク
自己肯定感が低い人は、断れないという人がとても多いです。
「本当はやりたくない」と感じたこと「相手に嫌われるかも知れない」という不安からやってしまっていることについて、”断る”ということをしてみましょう。
最初は、とても小さなことからでいいんです。それでも、勇気が必要だなと感じる人も多いはずです。
相手のお願いよりも、自分の「やりたくない」を優先してみましょう。
3.日記をつける
日記をつけるのは、自分の感覚・感情がわからなくなった人にとっても、とても効果があります。
最初は、一日の出来事を書き留めるだけでもOK。書けるようになってきたら、その時の自分の気持ちや、「どうしたかったか」まで書けるようになるといいですね。
コツは、朝に昨日の出来事を振り返って書いてみること。夜に書くとどうしてネガティブなことばかり考えてしまいます。特に自己肯定感が低い人は、それをきっかけに”自分責め”が始まってしまう人もいます。それではかえって苦しくなってしまいます。
私自身、苦しかった時には、日記を書き留めていましたが、続けていると、自分を客観視できるようになりますし、自分の気持ちが少しずつ出せるようになっていきました。文字にして出すことで、気持ちの整理にも繋がりますので、ぜひ続けてみてください。
🎁 お友達追加で受け取れます!
- 1日3行ログ
- 自分で満たせる私になるワーク
- “私が選ぶ条件”リストワーク
- 恋愛依存共依存セルフチェック
- 愛着スタイルセルフチェック
- 潜在意識の仕組み無料講座
自己肯定感を取り戻すカギは、“書き換え”ではなく“思い出す”こと
自己肯定感は、もともとあなたの中にあった感覚です。
それが、いつの間にか「◯◯しないと価値がない」「ちゃんとしないと認められない」といった“思い込み”によって、削られていってしまっただけです。
だからこそ、
日々の積み重ねて、少しずつ取り戻していくことができます。
今できる小さな一歩を大切に
自己肯定感を育てることは、単なる“ポジティブ思考”ではありません。
人生のすべての選択を、“自分の価値”を軸に決めていけるようになるということです。
恋愛も、仕事も、人間関係も。
「自分がどうしたいか」選んでいけるようになります。
FAQ|自己肯定感に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 自己肯定感を高めたいのに、なかなか変われません。どうすればいいですか?
▶ 自己肯定感は「努力で高める」ものというより、“本来の自分に戻る”ことで自然に育っていく感覚です。まずは、自分を責めている思考のクセに気づき、それを手放す練習から始めましょう。
Q2. 自己肯定感が低いと、人間関係もうまくいかないのでしょうか?
▶ 自己肯定感は人間関係にも影響します。自己肯定感が低いと、「嫌われないようにしなきゃ」と無理をしたり、「相手が喜ぶこと=正解」だと思い込んだりして、自分を見失いやすくなります。結果として、疲れる・満たされない人間関係になりがちです。
Q3. 自己肯定感が低くても、成功している人はいますよね?
▶ 社会的に、いわゆる”成功”と言われる状態の方ももちろんいます。ただ、「成果=価値」と思い込んで頑張り続けている状態は、内側に不安や孤独感を抱えていることも多いです。本当の意味での満足や幸福感を感じられず、燃え尽きてしまうケースもあります。内面から整えることで、成功も幸せも、両方手に入れられる状態をつくることができます。
Q4. 自己肯定感が低いのは、親のせいですか?
▶ 親の影響は大きいですが、「せい」として恨んだり責める必要はありません。大切なのは、“今の自分がそのパターンに気づいて、終わらせる選択ができる”ということです。
Q5. 自己肯定感を高める一番の方法は何ですか?
▶ まずは、本記事でご紹介したワーク、取り組んでみてください。

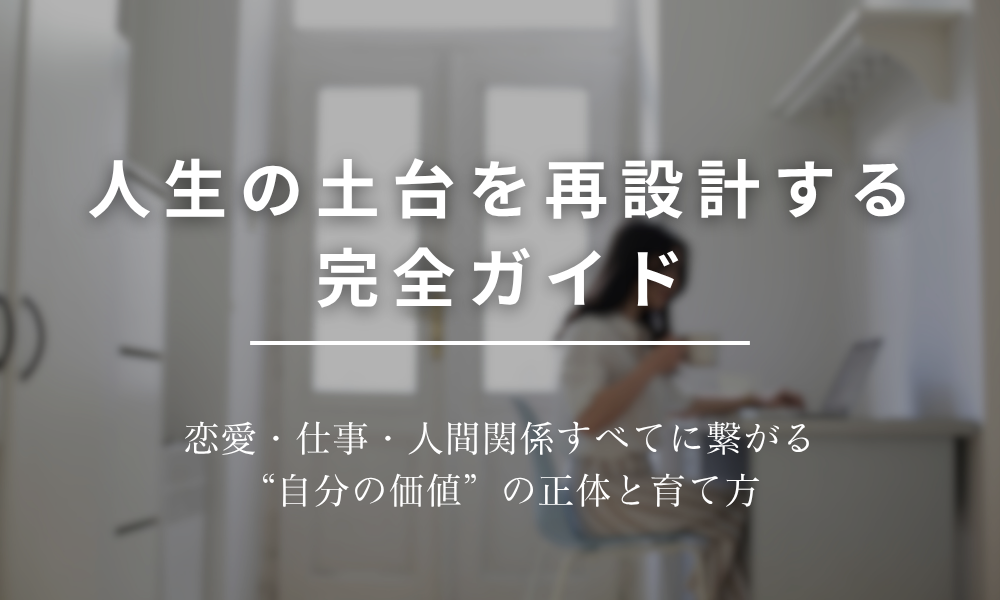

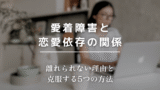

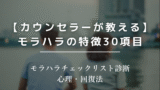
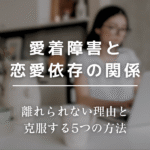
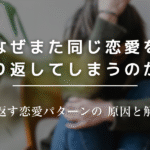
コメント